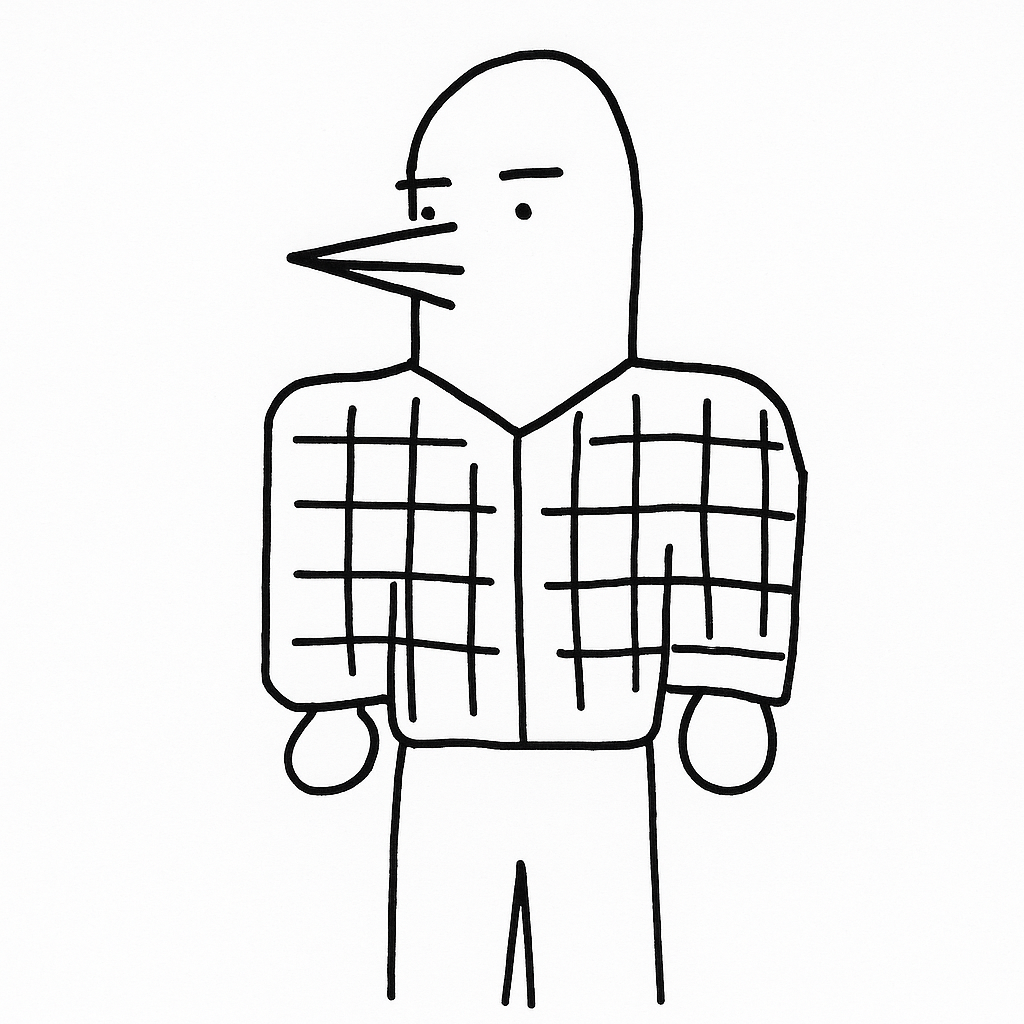こんにちは。気持ちよく仕事をするには、「自己受容感」「自己効力感」「他者貢献感」がかかせないと思っているasatoです。
ところで、これらが何なのかあまり言語化できていなかったので、ChatGPTに壁打ちをお願いしました。このポストは、そのメモです。
このポストのユーザーストーリー
- asatoは、
- これからも精神を安定させて気持ちよく仕事に取り組めるように、
- そのキーとなると思っている「自己受容感」「自己効力感」「他者貢献感」について言語化したい
それぞれの概要
自己受容感(Self-Acceptance)
とは?
自己受容感とは、ありのままの自分を受け入れられている感覚です。自己受容は、自己の強みや弱み、成功や失敗、外見や性格など、あらゆる側面を無条件に受け入れることを意味します。自己受容感が高いと、他人や環境の評価に依存せず、自分自身をそのままで価値のある存在だと感じることができます。
自己受容感は、他者の評価や批判から自由になり、自己を肯定的に捉える基盤となります。この感覚があると、自分に対して優しくなり、他人の期待に過度に応えることなく、自分のペースで生きることができます。
低い人・高い人
| 特徴 | 自己受容感が低い人 | 自己受容感が高い人 |
|---|---|---|
| 自己評価 | 自分の強みや弱みを受け入れられず、自己批判が強い | 自分の強みと弱みを受け入れ、ニュートラルに捉える |
| 他人との比較 | 他人と自分を比較し、劣等感を感じやすい | 他人と比較せず、自分自身をありのままで価値ある存在と認識する |
| 失敗への反応 | 失敗を自己否定と結びつけてしまい、落ち込むことが多い | 失敗を学びや成長の一環として捉え、次に活かすことができる |
| 自己批判 | 自己批判的な思考に陥り、自己評価が不安定 | 自分を大切に扱い、ポジティブな自己対話を行う |
| 他者の期待への対応 | 他人の期待に過度に応えようとし、自己を犠牲にしがち | 他人の期待を尊重しつつ、自分のニーズや感情も大切にする |
| 感情との向き合い方 | 自分の感情やニーズを無視しがち、自己表現が苦手 | 自分の感情に正直に向き合い、自己表現を大切にする |
| 自分を大切にする態度 | 自己ケアや自己成長を後回しにすることが多い | 自己ケアを大切にし、自己成長を意識的に追求する |
| プレッシャーへの対応 | 他人の期待に応えようと無理をして、ストレスが溜まりやすい | 自分のペースで行動し、過度なプレッシャーに悩まされない |
養い方
- 毎日「私はありのままで価値がある」と自分に言い聞かせ、過去の失敗も含めて自分を受け入れるようにする
- 自分がミスをしたとき、「次はどうすればよいか?」という学びの視点を持つようにし、自己批判的な思考をポジティブに転換する
- SNSや周囲の人との比較を避け、常に「自分にとって大切なこと」を基準に考える
- 日々、自己肯定的な言葉やポジティブな言葉を意識的に使う
- 「今、私は何を感じているのか?」と自分に問いかけ、その感情を否定せず正直に向き合う
- 定期的にリラックスする時間を設け、趣味やリフレッシュできる活動を積極的に行うことで、自己ケアする
- 毎日、達成した小さなことをノートに書き出し、「よくやった」と自分を褒める
自己効力感(Self-Efficacy)
とは?
自己効力感とは、自分には目標を達成できる能力があると信じる感覚です。自己効力感が高い人は、困難な状況にも前向きに取り組み、自分の力で問題を解決できると感じています。これにより、挑戦的な目標を設定したり、失敗から学びながら成長する意欲を持つことができます。
自己効力感は、行動を起こす際の自信やモチベーションに直接影響を与えます。高い自己効力感を持っていると、自分がやりたいことに対して積極的に取り組み、失敗や挫折を恐れずに挑戦し続けることができます。
低い人・高い人
| 特徴 | 自己効力感が低い人 | 自己効力感が高い人 |
|---|---|---|
| 目標へのアプローチ | 挑戦を避ける、目標に対して消極的 | 挑戦を受け入れ、積極的に取り組む |
| 失敗への反応 | 失敗を自分の限界と結びつける、自己否定的 | 失敗を学びの機会として捉え、前向きに改善策を考える |
| 自己評価 | 自分に対して自信がなく、自己評価が低い | 自分の能力を信じ、自己評価が安定している |
| 困難に対する態度 | 困難に直面するとすぐに諦める | 困難を乗り越えるための方法を考え、粘り強く取り組む |
| 他人との比較 | 他人と比較し、自分が劣っていると感じる | 他人と比較せず、自分のペースで進む |
| 問題解決力 | 自分の力で問題を解決するのに不安を感じる | 問題を自分の力で解決する能力に自信がある |
| 挑戦的な目標の設定 | 達成可能な小さな目標にとどまることが多い | 大きな目標に挑戦し、それを達成できると信じている |
| ストレス耐性 | ストレスに弱く、プレッシャーに圧倒されることが多い | ストレスやプレッシャーにも冷静に対応できる |
養い方
- 目標を小さく設定し、小さな成功体験を積み重ねることで自信を深める
- 自分が達成したことを振り返り、「よく頑張った」「次はどうするか?」とポジティブなフィードバックを与える
- 失敗したときには、それが一時的な結果であり、次の成功に繋がる学びであると考え、改善策を立てて前向きに取り組む
- 自分がどれだけ成長したかを記録し、定期的にそれを振り返る
- 必要なときに、他人に助けを求めることで、孤立せずに自信を持ち続けることができる
- 自分にとって少し難しい目標を設定し、それに挑戦することで達成感を得る
他者貢献感(Sense of Cotribution)
とは?
他者貢献感とは、自分の行動や努力が他人や社会にとって価値があると感じる感覚です。自分が他者に役立つことができる、社会に貢献しているという実感は、自己価値感や幸福感を高め、自己満足感にも繋がります。人は他者貢献感を感じることで、自分の存在が他者にとって意味があることを実感し、その結果として自己成長や社会的つながりを強化できます。
他者貢献感が高い人は、他人を支えたり助けたりすることに喜びを感じ、自分の時間やエネルギーを有意義に使っていると感じます。反対に、他者貢献感が低い場合は、他人のために何かをすることに価値を感じにくく、孤立感や無力感を抱えることが多くなります。
低い人・高い人
| 特徴 | 他者貢献感が低い人 | 他者貢献感が高い人 |
|---|---|---|
| 他人への配慮 | 他人に対して無関心、自己中心的になりがち | 他人のニーズや感情を理解し、積極的に支援する |
| 行動の動機 | 自分の利益や快適さを最優先する | 他人や社会のために行動し、貢献することに喜びを感じる |
| 幸福感の源 | 幸福感が自己中心的な成功や物質的なものに依存 | 幸福感を他人の感謝や満足、社会的な貢献に見出す |
| 自分の役割の認識 | 自分の役割が限られ、他者と関わりを持つことに対して消極的 | 自分が他者に貢献できる存在であることに誇りを持つ |
| 人間関係の形成 | 他人とのつながりが希薄で孤独を感じやすい | 支え合いの関係を築き、他人とのつながりを大切にする |
| 社会的な責任感 | 社会への貢献や責任感を感じることが少ない | 社会の一員として、自分ができる範囲で積極的に貢献しようとする |
養い方
- 他人の手助けが必要な場面で積極的に支援を申し出る、またはボランティア活動に参加する
- 自分のスキルや知識を他人と共有し、他者が成長できるようサポートする
- 他人の感情に耳を傾け、共感し、理解を示すことで深い人間関係を築く
- 他人の成功や喜びに共感し、一緒に喜びを感じることで、社会的なつながりを強化する
- 小さな親切や気配りを意識的に行い、他人の生活にポジティブな影響を与えることを心がける
- 自分の活動がどのように他者に貢献しているかを振り返り、その感覚を意識的に味わう
- 自分の仕事や役割を通じて、社会にどんな影響を与えているのかを考え、その貢献を誇りに感じる
それぞれの関係性
- 自己受容感は、自分のありのままを受け入れる感覚であり、他の2つの感覚の基盤になる。これが低いと、自分の能力や行動に自信を持ちにくくなる。
- 自己効力感は、「自分には目標を達成する力がある」と信じる感覚。自己受容感が高いと、自分の強みや成長の可能性に意識が向くようになり、自己効力感も高まりやすくなる。
- 他者貢献感は、「自分の行動が他者や社会に役立っている」と感じる感覚。自己効力感が高いと、「自分は人の役に立てる」という自信が生まれ、他者貢献感につながりやすくなる。
BTW:アドラー心理学
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、「自己受容」「他者貢献」はアドラー心理学から来ています。かなり自分の人生観に影響を受けていますね。
アドラー心理学って何?という方は、以下の書籍がおすすめです。
まとめ
- 自己受容感:ありのままの自分を受け入れている感覚
- 自己効力感:自分には目標を達成できる能力があると信じる感覚
- 他者貢献感:自分の行動や努力が他人や社会にとって価値があると感じる感覚
この3つの感覚が自分にとって楽しく働くキーになっています。ChatGPTのおかげで言語化ができたし、養い方も教えてもらえたので、なんだかうまくいかないなって時はここに戻ってこようと思います。
サポートもお待ちしております!