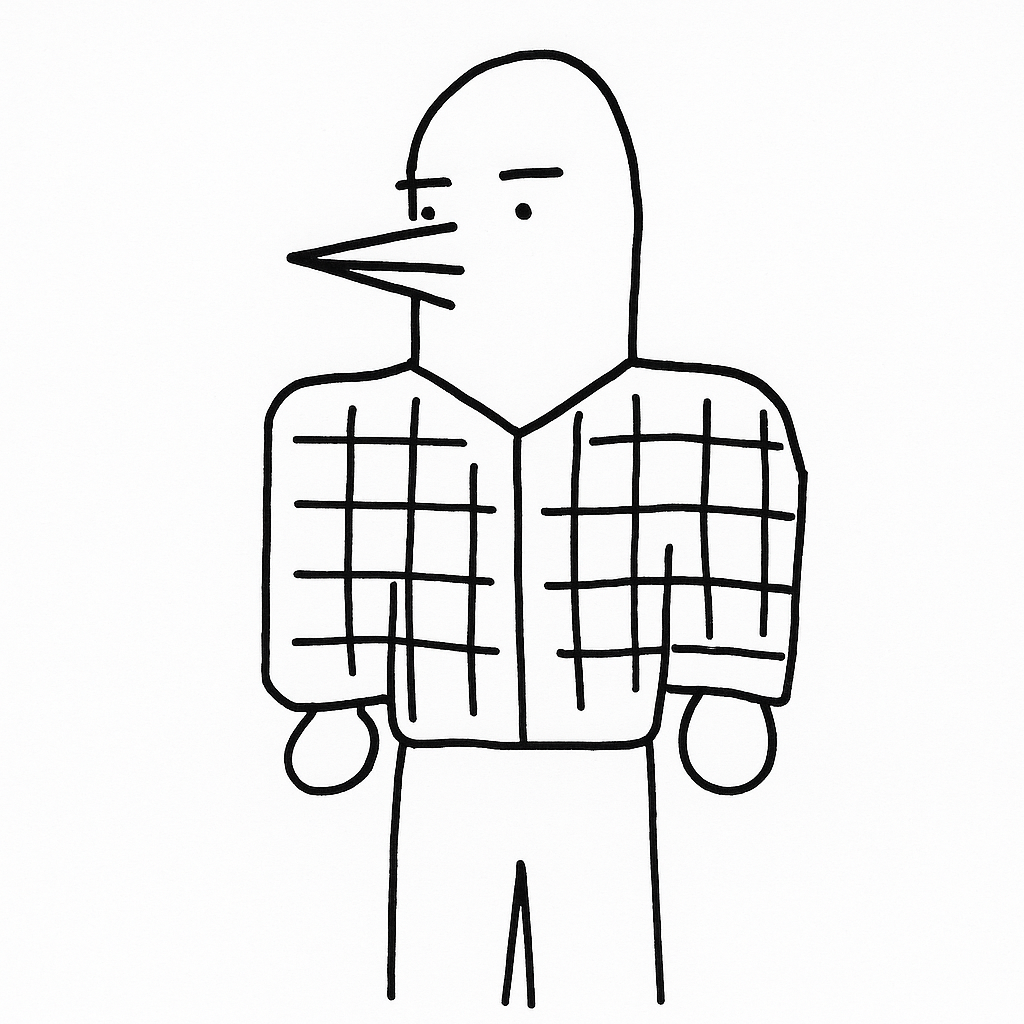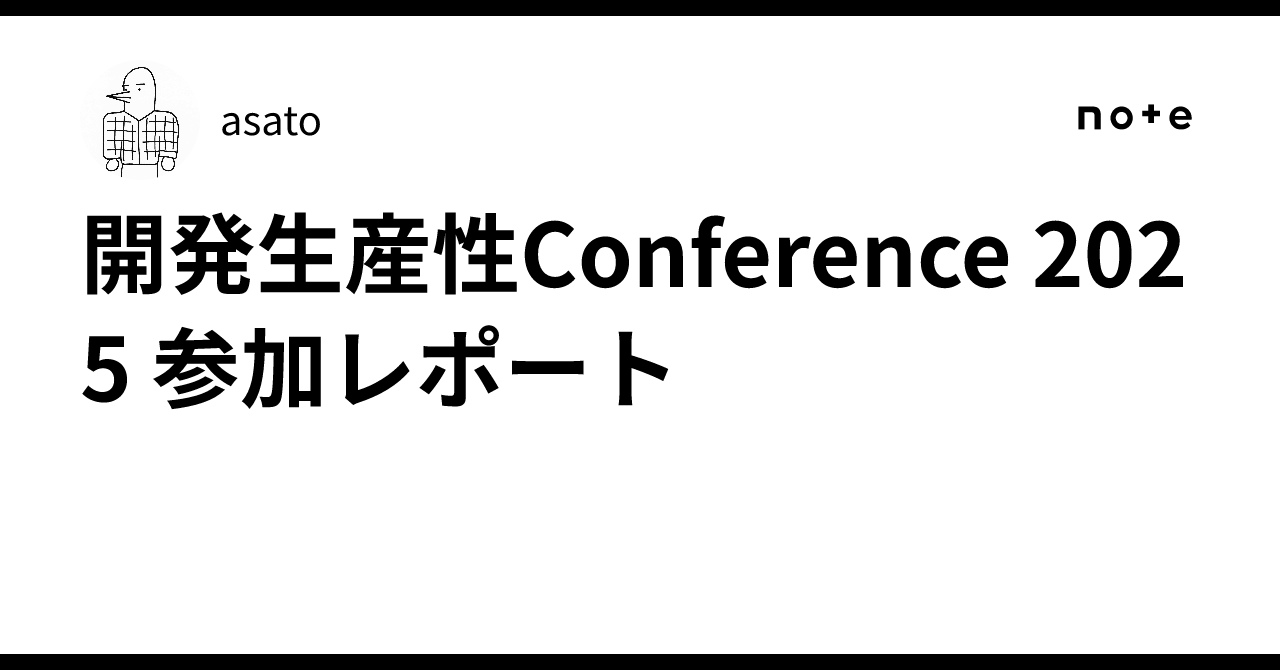
1. 基本情報
- カンファレンス名:開発生産性Conference 2025
- 開催日時:2025年7月3日(木)4日(金)9:30〜19:00
- 開催場所:JRタワーホール&カンファレンス
- URL: https://dev-productivity-con.findy-code.io/2025
2. 参加目的
- 「開発生産性」に関する情報収集、動向把握のため
3. 概要
「開発生産性Conference 2025」は、生成AI時代における開発生産性と事業価値の向上をテーマに、国内外の著名エンジニアや経営者が実践知や最新事例を共有するカンファレンスです。 Kent Beck氏やGene Kim氏の基調講演をはじめ、2日間で約60のセッションが提供されました。
4. 学び・気づき
Outputよりも先にOutcomeやImpactに目を向ける
「開発生産性」と聞くと、Four KeysやPR数、SLOCなどのOutputに関する指標が思いつくかもしれません。 しかし、本カンファレンスでは基調講演を含むほとんどのセッションで、Outputよりもより目的に近いOutcomeやImpactに目を向けることが提案されていました。
『開発生産性測定のトレードオフ 「グッドハートの法則」はもっと悲観的に捉えるべきだった』
Kent Beck氏による基調講演では、「Effort、Output、Outcome、Impact」というループが提案されていました。 そして、このループにおいてより計測や制御のしやすい提供者側のEffortやOutputに注目しがちになるが、本当に重要なものは提供先のOutcomeやImpactであることが示されていました。 また、「ある尺度が目標になると、それは良い尺度ではなくなる」というグッドハートの法則にも触れられていました。 自分たち自身の分析のために指標を図ることは大切である一方、それ自体を制御しよう(プレッシャーを与えよう)とするとむしろ状況は悪化すると述べていました。
本セッションの内容は、同氏が書かれたブログ『 Measuring developer productivity? A response to McKinsey 』からもうかがい知ることができます。
『開発組織の進化・スケーリングと「開発生産性」』
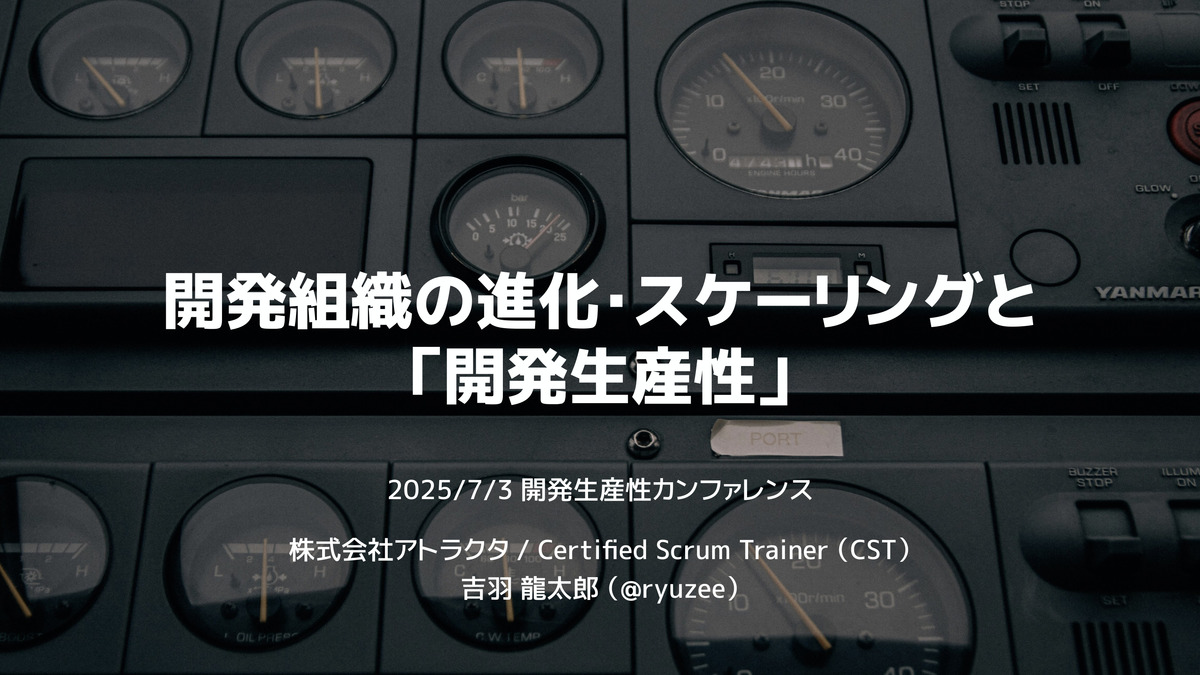
株式会社アトラクタ 吉羽氏の『開発組織の進化・スケーリングと「開発生産性」』では、関心を寄せるべき開発生産性はプロダクトやチームのフェーズによって違うということを提案し、その例を示されていました。 そして、ある程度の規模の会社の中にはさまざまなフェーズのプロダクトチームが混在しているため、全社で画一的な指標を導入し開発生産性を測ろうとすることは困難であると述べていました。 一方で、「エンゲージメント」に関しては、どんなフェーズのチームにおいても計測してみる価値のある指標であるとの言及は興味深いものでした。
現在、スクラムマスターとして働いている私としては、「イネイブリングチームに定量化の力がかかると余計な仕事ばかりするようになる」という言葉に共感しました。 また、そのような人たちの成果を測るためには、いわゆる360°評価などが有効であるという話にも納得しました。
経営指標と開発生産性を紐づけるセッションも多かった
セッションの中では、開発生産性を測る指標として経営指標( EBITDA 、 ROIC など)と開発を紐づける試みを実践している事例も多くありました。 これは、経営層に対し「開発組織は生産的に働けているのか」という問いに対する答えとして、経営層の関心事で回答する素晴らしい試みだと感じました。 ソフトウェアエンジニアが経営層の関心事に関心を向けるきっかけにもなります。
一方で、これだけだとプロダクトの利用者ではなく、経営層や投資家、株主に目が向きやすくなってしまうのではないかという懸念も感じました。
『“いい感じ“な定量評価を求めて - Four Keysとアウトカムの間の探求 -』
株式会社ニーリー 三宅氏の発表にある、OutcomeとOutputから自分たちの開発力を判断しようとする試みは興味深かったです。 このセッションでは、完了した開発案件の規模、リードタイム、KPI達成度などから「開発組織は生産的か?」の問いを見つけ出そうとしていました。 Effort/Outputだけだと本来の目的を見失い、Outcome/Impactだけだと開発組織の貢献度が見えにくくなる中で、その双方の指標を同時に見ることは効果的であると感じました。
AIを前提に仕事を設計していないことに気づいた
今回の開発生産性カンファレンスでは、生成AIを扱ったセッションも多くありました。 生成AIが開発生産性にどのような影響を与えているかの事例紹介もありましたが、「生成AIを前提として全体のフローを再構築できているか」というメッセージのセッションが特に気づきを与えてくれたと感じました。
『ソフトウェアエンジニアリングの人類史 〜AI エージェント時代の知識創造企業〜』
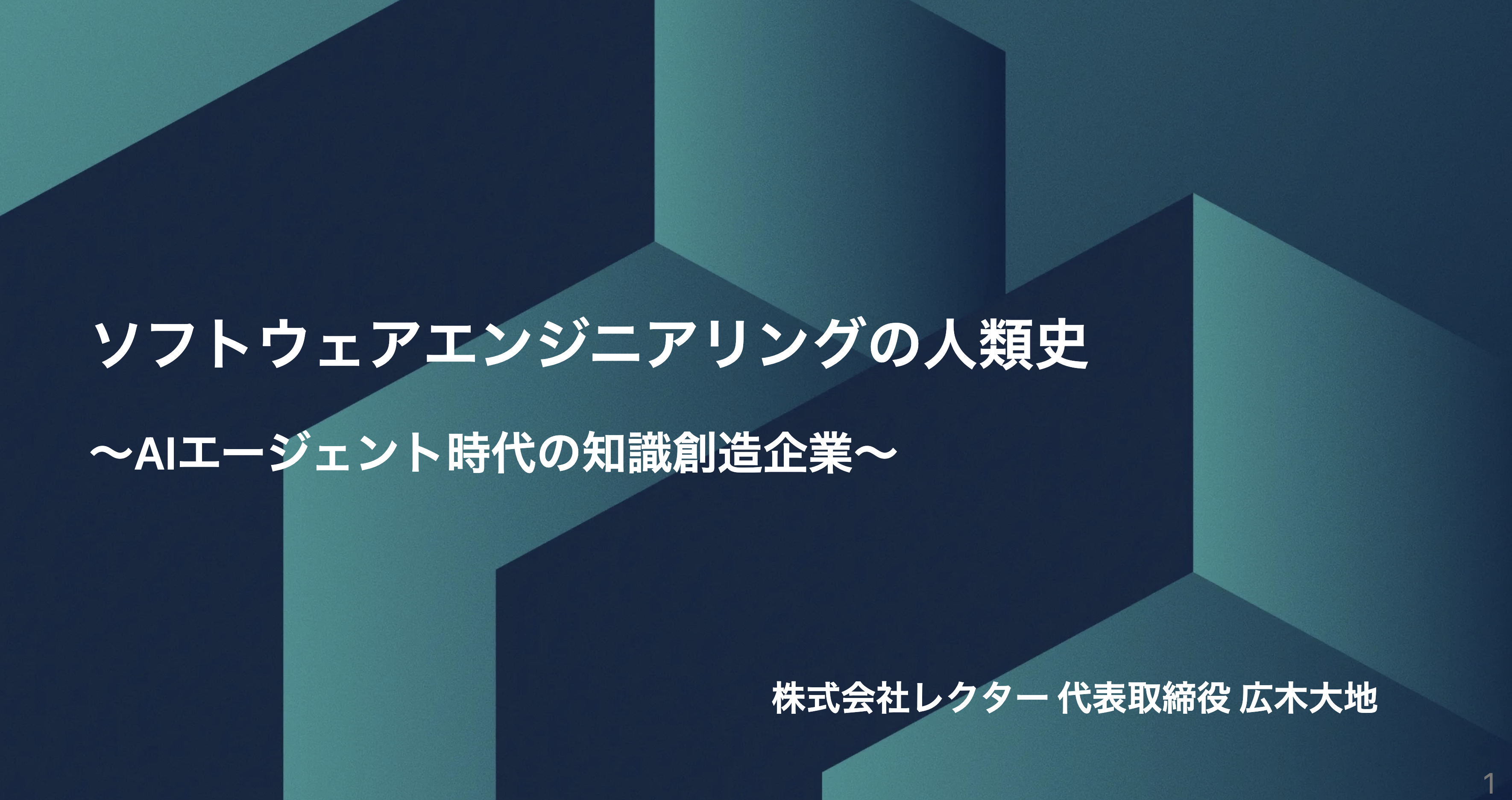
株式会社レクター 広木氏のセッションでは、「AIが仕事を奪う」と言われている中で、「いままでだって人間はなにかに仕事を奪われてきた」ということを気づかせてくれる内容でした。 例えばロボットやコンピュータ、もっと遡れば「識字の普及」でさえ、誰かの仕事を奪ってきています。となれば、AIの台頭に対しても、人間は適応していくしかありません。 セッションでは、AIエージェントが組織のナレッジマネジメントを自律的に担い、改善していく可能性にも言及されており、より大きな枠組みでのAI活用を想像しておく必要性を感じました。
『無意味な開発生産性の議論から抜け出すための予兆検知とお金とAI』
合同会社DMM.com 石垣氏のセッションでも、「AI-BPR」としてAIを前提とした全体プロセスの再構築に言及されていました。 現在は、コーディングやPRD作成などのある役割に閉じた局所的なAIの活用が取り上げられているが、プロダクト開発ライフサイクル全体でAIはどう振る舞えるのかを検討することの重要性を認識しました。
また、「AIによって『開発生産性』は気にならなくなるほどスピードが上がる」という話もありました。 たしかに、今はアウトプットのスピード感の期待のギャップから「開発生産性」にスポットライトがあたっているのであって、AI Agentのスピードが前提となれば関心事は別の場所に移るのだろうと感じました。
AI時代のソフトウェア開発を考える
Day2のクロージングキーノートであったタワーズ・クエスト株式会社 和田氏のセッションはまた別の切り口でした。 Vibe CodingやClaude Codeが騒がれる中、果たしてそちらだけに舵を切れるのかという話だと受け取りました。 最初から正しい設計ができることはなく、コードを書き始めてから気づくのが世の常です。 AI Agentとのコーディングはその気づきの機会を失うことになるのではないかという問いには頷けました。
AIとの伴走、AIへの委託という二つのモードについても言及されていました。 さらに壁打ち相手、教師としてだけAIを使ったり、AIを使わずに人間がコードを書く選択肢もあります。 「Whether or not(AIを使うべきかどうか)」ではなく「Compare and Contrast(比較と対比)」。 さまざまなオプションを試して使い分けていく必要があるとのことでした。
人と人がつながる文化の大切さ
また、アウトプットやアウトカムだけでなく、人と人がつながる文化、まさにエンゲージメントやウェルビーイングの部分が依然大切であると感じました。
『コードのその先へ:開発者体験を活性化させる方法』
Netflix, Inc. Kate Wardin氏のセッションでは、Netflixで開発生産性、開発者体験を向上させるための取り組みの事例が紹介されていました。 「持続可能な生産性」が大切であると言及されており、「コミュニケーション」「心理的安全性」「フロー体験」などの定性的な計測やアプローチが多く語られているのが印象的でした。 また、それらの指標は「開発者をアウトカムに注目させられているか」をベースに評価し直されるという話もあり、人と人のつながりと集中できる環境の両立に対して熱心に取り組まれている様子がわかりました。
Q&Aでは「Netflixではハイパフォーマー以外はfireする文化と聞いているが、その中で高い心理的安全性を保つのはどうしているのか?」という質問がありました。 これに対して、「頻繁で率直なフィードバックの文化が心理的安全性を高めている」と回答しており、フィードバックの無さが心理的安全性を低下させることに気付かされました。
『開発生産性を測る前にやるべきこと:組織改善の実践』
株式会社カオナビ 富所氏のセッションでは、株式会社カオナビで組織をよりよくするために実施されている数々の施策が紹介されていました。 イベントの企画からテクニカルな施策までさまざまありましたが、どれも職能間またはチーム間のサイロ化を壊すために設計されており、とても良い組織文化なのだと感じました。
セッションの中で、「1人では難しいが、3人いれば取り組みを続けることができる」という発言があり、まずは3人の仲間を探すことから始めようと思いました。
(ちなみに私の前職ですが、そういうのを抜きにしていいセッションだったなと思ったので載せてます。)
5. まとめ
開発生産性Conference 2025を通して、開発生産性を「数字で測ること」以上に「本来の目的にどう近づいているか」を見極める重要性を再認識しました。特に、OutcomeやImpactへの視点や、生成AIを前提とした全体設計、人と人がつながる文化の大切さなど、多面的な学びが得られました。これらの視点を、スクラムマスターとしてのチーム支援や組織改善の実践に活かしていきたいと思います。
サポートもお待ちしております!