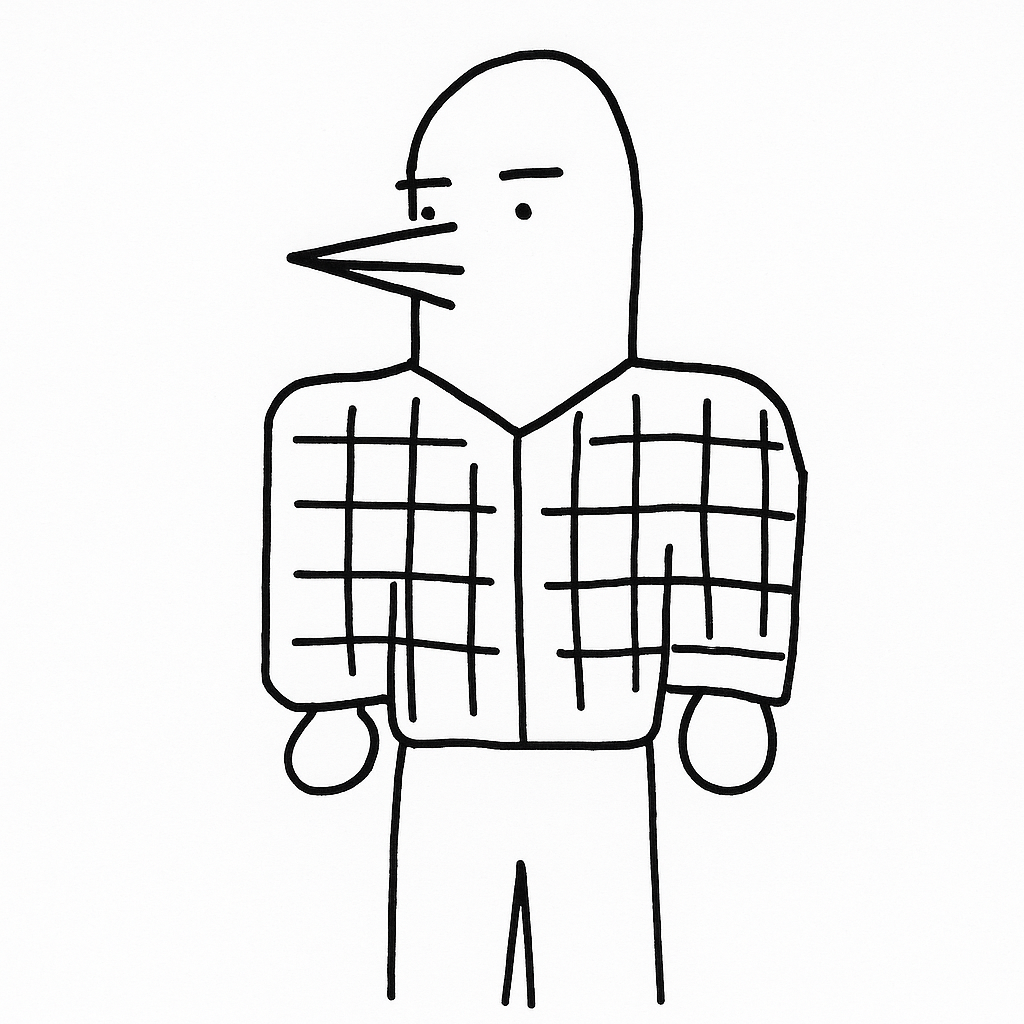「自律的なチーム」をつくるためには、「自律的な環境」が先か、「自律できるだけのスキル」が先か、という話をよく見聞きします。自律的なチームは大切だが、あのチームはまだ自律するだけのスキルを持っていない。だから、マネージャーの指示や組織の標準に従ってスキルを身につけたのち、自律的な環境を用意する。そんな話です。
こちらは、それが効率的かつ効果的な道なんだっけ?というブログです。
自律的なチームは、「信頼」の上に生まれる
もしあなたがスキーができるようになりたいなら、スキー板を持って雪山に行くでしょう。可能であれば、目指す状態を経験できる環境で練習をしたくなるはずです。少なくとも水着を片手に海に行くような、真逆の選択はとらないはずです。
僕は、自律的なチームになるための道も同じことだと考えています。自律的なチームになるには、自律的なチームとして扱われる環境が必須であり、もっとも効果的かつ効率的な道です。誰かの指示や標準に従っていくなかで突然自律的なチームになれるのではなく、自律的なチームとして扱われる中で試行錯誤した末に自律的なチームになれるということです。
そのために必要なものは、チームのステークホルダー、もっと言えばマネージャーなどチームをマネジメントする立場からの「信頼」です。
嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え他者を信じるにあたって、一切の条件をつけないことです。たとえ信用に足るだけの客観的根拠がなかろうと、信じる。担保のことなど考えずに、無条件に信じる。それが信頼です。
1兆ドルコーチ――シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教え「信頼」とは、彼らに自由に仕事に取り組ませ、決定を下させることだ。彼らが成功を望んでいることを理解し、必ず成功できると信じることだ。
アジャイル宣言の背後にある原則意欲に満ちた人々を集めてプロジェクトを構成します。環境と支援を与え仕事が無事終わるまで彼らを信頼します。
まず、チームを信頼し、「自律的なチーム」の環境を与えてあげてください。そして、支援を与えてください。困ったときにいつでも相談できる場や関係性、大失敗を回避するためのガードレール、あなたのもつ情報の透明化などがあります。
目の前のチームはあなたからみればたしかに未熟で危なっかしく見えると思います。それでも「自律的なチームとして扱われている環境」が自律的なチームに成るためには不可欠で、効果的です。まず、信頼してあげてください。
自律的なチームは、「信用」の上に存続する
マネージャーの勇気ある信頼の上に、自律的なチームが生まれました。このチームが自律的なチームであり続けるためには、「信用」を得続けなければなりません。チームメンバーは一丸となって、ステークホルダーの信用を勝ち得なければならないのです。
何をすれば信用を勝ち得られるのでしょうか?それは、ステークホルダーによって異なります。その立場ごとに、もっといえばその人ごとに違ったものさしであなたのチームが信用できるかどうか測っています。
まずは、自分たちのステークホルダーとは誰なのかを知ること。そして、その人たちそれぞれのものさしを知ること。そのものさしで信用に足る結果を見せること。
信頼の上に自律的に動ける環境を手に入れたチームは、それを確固なものにするために信用を勝ち得なければいけません。信頼はそれほど長続きしません。信頼という地盤が揺らぐ前に、自分たちには自由を与えておけば大丈夫と思ってもらえる感覚を持ってもらいましょう。
自分たちだけが信用を得ても足りない、だから広げる
自分たちだけが信用を勝ち得ても足りないことがあります。どれだけ自分たちのチームが自律的に動けていても、あなたの所属する組織レベルで見たときに信用がなければある日突然その環境は一変する危険性があります。僕もこういう経験があります。
ナレッジをシェアしましょう。あなたがいかにして信用を勝ち得ているのか。どのステークホルダーがどんなことに興味を持っているのか。どううまくやれているのか。
あなたのチームだけでなく、ほかのチームも自律的に動けるチームになるよう協力し合いましょう。働きかけあいましょう。それがあなたのチームの自律性を守ることにもつながっていきます。
それでも一番見るべきは顧客
自律的なチームを維持するためには、ある程度社内のステークホルダー、特にレポートライン上のステークホルダーに関心を寄せる必要があることに言及してきました。
しかし、それでも一番関心を寄せるべきは顧客です。これは忘れてはいけない。なんならステークホルダーの関心事も顧客の関心事に寄せていくような働きかけができれば、気にしなければならないことは減りよりシンプルにできます。これを目指していきたいところ。
さいごに
このブログでは、自律的なチームがどのように生まれ存続するのかについての持論をまとめました。僕もうまくいったこともあればそうでないこともあります。そうでないほうが多いです。悲しい。でもその経験から、今のような考えに至っています。引き続きがんばるぞ。
このブログが、どこかの誰かのなにかのきっかけにでもなったら嬉しいです。
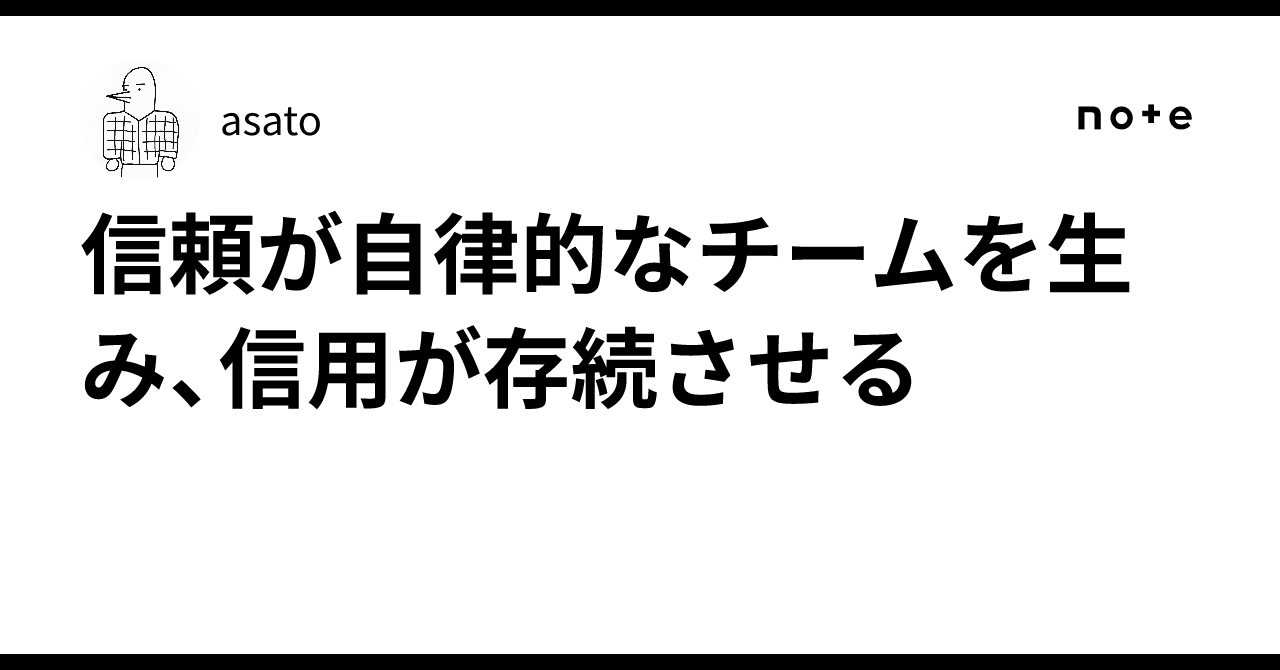
サポートもお待ちしております!